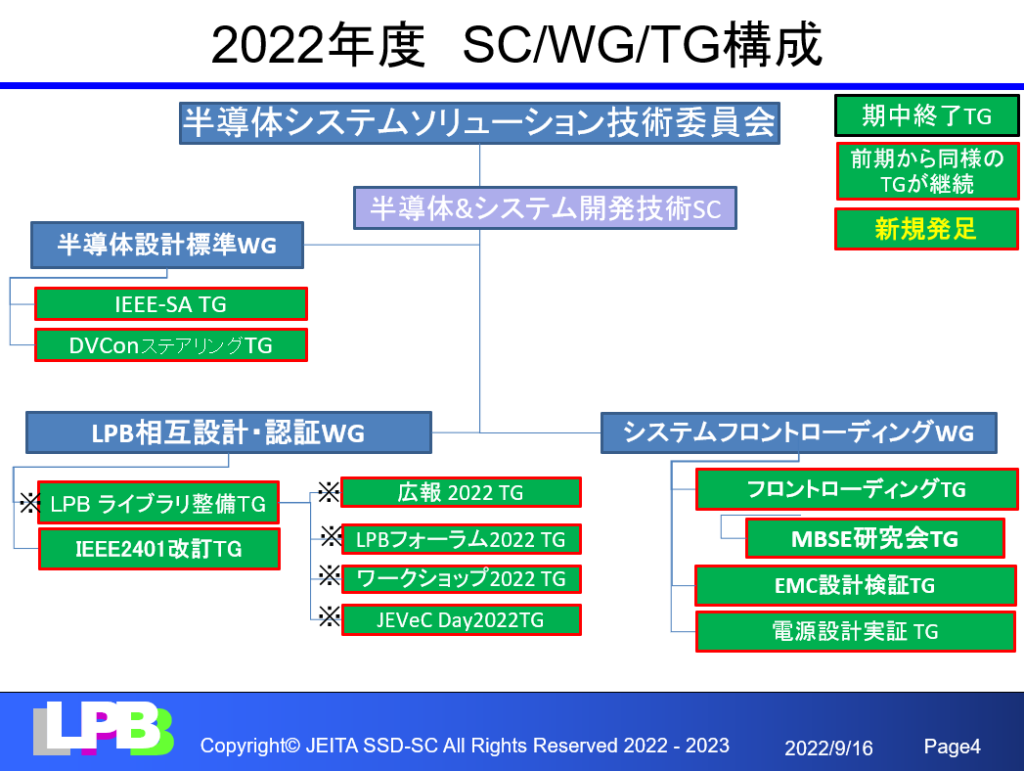━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第93号 LPBニュース 2023年1月24日配信
半導体&システム設計技術委員会編集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★★★★ 今回のトピックス ★★★★★
■JEITA 第15回LPBフォーラム 開催いたします。
■イベント情報
【1】JEVeC DAY 2022 申込受付中(締め切り1/27)
【2】2022年度 半導体EMCセミナー 申込受付中(締め切り1/27)
〜 半導体EMC国際規格の動向とロボットのEMC 〜
───────────────────────────────────────────
■JEITA 第15回LPBフォーラム 開催のお知らせ
日時: 2023年3月3日(金)13:30〜
会議方式:リアル+オンライン(リアル開催は大手町ファーストスクエアカンファレンス予定)
詳細 URL:準備中(2月予定)
───────────────────────────────────────────
LSI - Package - Board(略してLPB)の協調設計を議論する誰でも参加できるコミュニティー
として開催してきましたLPBフォーラムも15回目を迎えることになりました。
3月3日(金)13:30より開催いたします。ご予定いただければ幸いです。
今回はリアル+オンラインのHybrid開催の予定です。鋭意準備を進めております。
参加者の皆様からもご意見を頂きたく、是非ご参加ください。
プログラム(暫定)
・開催にあたって
・電子デバイスモデル仕様書標準化の必要性調査報告の概要紹介
・MBSE/MBDによる設計フロー構築とLPBフォーマットの活用
・休憩
・フロントローディングの領域拡張
『EMCフロントローディング設計 いろいろ』(仮)
・閉会の挨拶・連絡事項
───────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────
■イベント情報
───────────────────────────────────────────
【1】JEVeC DAY 2022 申込受付中
───────────────────────────────────────────
お申込みはこちら: https://www.jevec.jp/jevecday2022/2022register/
───────────────────────────────────────────
JEITA LPBはJEVeC DAY 2022に出展し、技術セミナーと技術展示を行います。
日本EDAベンチャー連絡会(JEVeC)は、国内のEDA関係者が一堂に会して「技術討議できる」場
を提供すべく、今年度も、「講演会」と「技術展示」を一体化したJEVeC DAYを開催いたします。
「講演会」では、上流から下流まで、最新の技術動向を仕入れていただける講演を取り揃え
ました。また、初の試みとして、海外の新進気鋭のEDAベンダの講演も用意いたしましたので、
是非、ご注目ください。さらに、恒例のチュートリアルでは、アナログ回路設計をテーマに、
基礎から最新動向までをご紹介いたします。
「技術展示」では、16社の現場の技術者がブースでお待ちしております。製品・サービスの
ご紹介のみならず、込み入った技術相談も大歓迎です。
感染症の状況によっては変更する可能性もありますが、ご来場いただいた皆さま、および出展社が
気軽に交流いただけるよう仕掛けも用意する予定ですので、是非、現地まで足をお運びください。
スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
日時: 2023年1月31日(火)10:20〜19:30 (受付開始:10:00)
会場: 川崎市産業振興会館
講演: 1階ホール(10:20〜18:00)
技術展示: 4階展示会場(12:00〜18:00)
主催: 日本EDAベンチャー連絡会(JEVeC)
企画・運営:JEVeC DAY 2022 実行委員会
参加費: 無料(事前登録制)
締め切り: 2023年1月27日(金)
詳細: https://www.jevec.jp/jevecday2022/
是非、参加のお申込みをお願いいたします。
https://www.jevec.jp/jevecday2022/2022register/
◆ 技術セミナー
10講演
「JEITAの活動紹介 MBSEを活用したカレー作りと電子機器設計」黒?幸司 氏
一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)半導体&システム開発技術委員会 委員
◆ 展示会
展示 16 社
「JEITA半導体&システム開発技術SCの活動紹介と会員募集」一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)
「CR-8000 Design Forceによるデバイス設計革新」株式会社図研
───────────────────────────────────────────
【2】2022年度 半導体EMCセミナー 申込受付中
〜 半導体EMC国際規格の動向とロボットのEMC 〜
───────────────────────────────────────────
お申込みはこちら: https://www.jeita.or.jp/form/custom/238/form
───────────────────────────────────────────
JEITA半導体システムソリューション技術委員会・半導体EMCサブコミティ(SC)では、半導体
デバイスのEMC(Electromagnetic Compatibility:電磁環境両立性)についてのご理解を一層深
めていただくために、2015年度に始まり毎年恒例となりました本セミナーを開催します。2022年
度のセミナーもコロナ禍のためWeb会議形式とし、聴講料無料にて3時間行います。
本セミナーでは、まずは当サブコミティのより『半導体EMC国際規格動向とJEITA活動』と題して、
IECの半導体国際規格のトピックス並びに、規格/実証実験の活動内容等について紹介します。
そしてその後、実際のアプリケーションの具体例としてロボット業界から、『パワード義足のEM
C』(BionicM株式会社)並びに『三菱電機のFA機器ならびに産業用ロボットにおける、EMC対策
の取組み紹介』(三菱電機株式会社)と題してご講演頂きます。皆様においては、最近好調なロ
ボット業界におけるEMC動向についてご理解頂くと共に、ご自身のEMC設計・評価へのフィード
バックを図って頂ければと思います。
時節柄、業務ご多用のことと存じますが、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
【開催概要】
日時: 2023 年2月3日(金) 14:15〜17:15
開催方法: Webexによるリモート開催
※参加用のミーティングリンクは登録完了メールに記載しておりますのでご確認願います。参加
を希望される方は事前にWebexアプリケーション並びに利用につきまして各自にてご確認願います。
主 催: (一社)電子情報技術産業協会
半導体標準化専門委員会/半導体システムソリューション技術委員会/半導体EMCサブコミティ(SC)
参加費: 無料
参加方法: 申込後、メールにて
詳細: https://www.jeita.or.jp/japanese/exhibit/2023/0203.pdf
申込期限:2023年1月27日(金)まで
https://www.jeita.or.jp/form/custom/238/form
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
LSI・パッケージ・ボード(LPB)相互設計規格である国際標準IEC 63055/
IEEE 2401-2019は下記URLからご購入できます。
https://standards.ieee.org/standard/2401-2019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Jeita SDTC http://www.jeita-sdtc.com
LPB Forum http://www.lpb-forum.com
Facebook https://www.facebook.com/lpbforum/
Twitter https://twitter.com/lpb_forum
◆本メールマガジンは、LPBフォーラムに御参加いただいた皆さまに
各種イベントやセミナー情報を配信させていただくものです。
配信停止は下記URLからお手続きください。
配信停止用URL: http://jeita-sdtc.com/xmailinglist/news/
◆新たに配信をご希望される方は下記URLからお手続きください。
JEITA半導体&システム設計技術委員会メールマガジン
※このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。このままご返信
いただいてもお答えできませんのでご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C) 2017 JEITA 半導体&システム設計技術委員会
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━