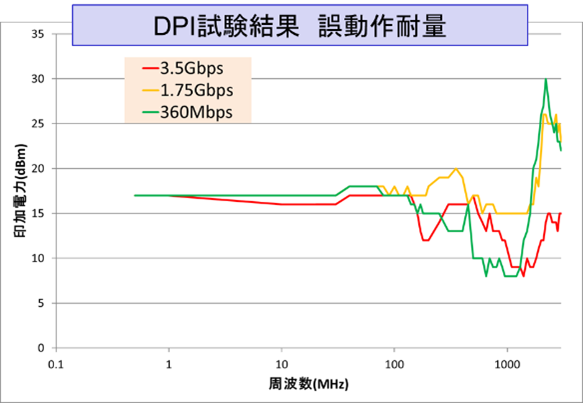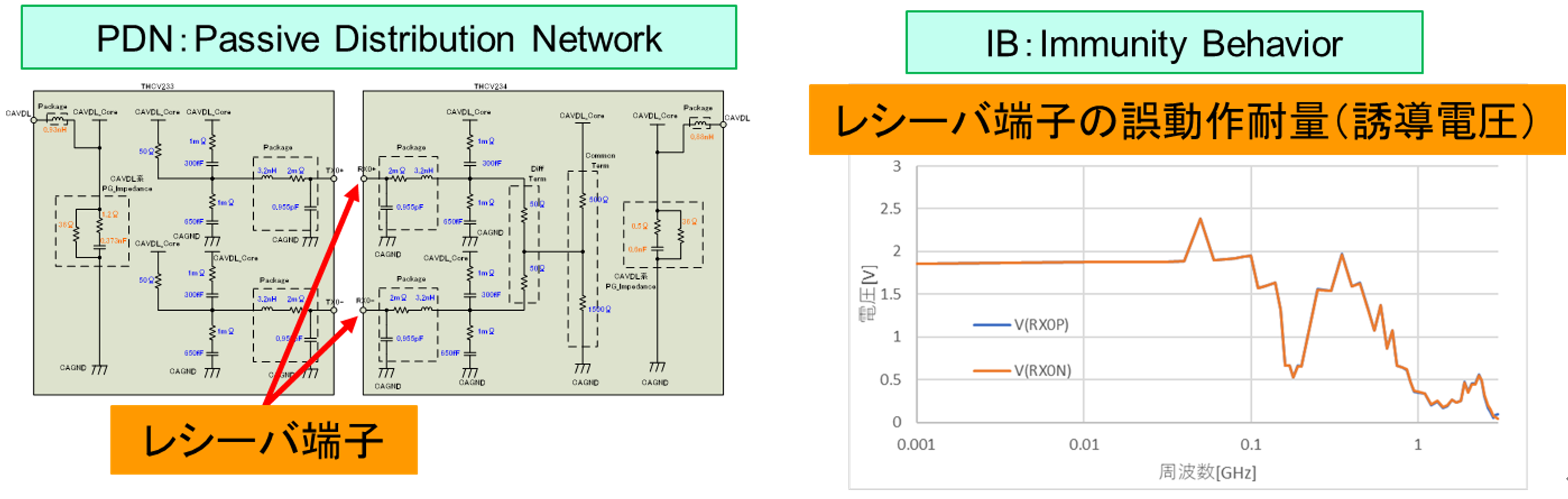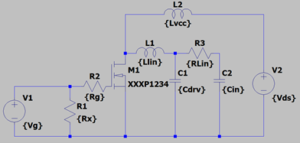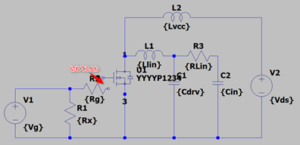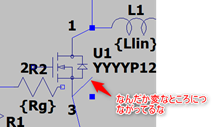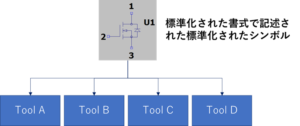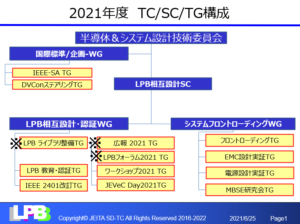━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第88号 LPBニュース 2022年8月10日配信
半導体&システム設計技術委員会編集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★★★★ 今回のトピックス ★★★★★
■JEITA LPBフロントローディングワークショップ2022(Web)開催!
■「今月の活動紹介」第8回 EMC設計実証TG
■イベント情報
【1】【 PCB Systems Forum 2022 】
───────────────────────────────────────────
■JEITA LPBフロントローディングワークショップ2022(Web) 開催!
───────────────────────────────────────────
参加申込: https://www.jeita.or.jp/form/custom/182/form
───────────────────────────────────────────
日 時 : 2022年9月9日(金)13:00~17:00
会議方式 :Webex
詳細 URL : http://jeita-sdtc.com/2022/08/lpb_workshop2022/
今回のLPB Forumは、例年と趣向を変えて、MBSEの体験会、3Dモデルについて聴講者の皆様と
議論するLPB Workshopとしたいと思います。
奮ってご参加ください。
プログラム(暫定)
・開催にあたって
・MBSEの体験会
・3Dモデルについての議論
・閉会の挨拶・連絡事項
───────────────────────────────────────────
■「今月の活動紹介」第8回 EMC設計実証TG
───────────────────────────────────────────
今回は、「EMC設計実証TG」の活動を紹介します。
本TGでは、比較的難易度の高い2つのモデルにフォーカスしてそのモデル化手法と活用手法を
議論しております。
一つは、ICIM-CI(Conducted Immunity Modelling)と呼ばれるモデルでシステムのBCIや
ESD試験いわゆるイミュニティー試験での誤動作予測に使えるモデルです。
もう一つはICEM-RE(Radiated Emission Modelling)と呼ばれるモデルでLSIの直接放射が
ヒートシンクに結合するEMIの問題、機内配線へ結合する自家中毒の問題を予測することを
目指しています。
今回は、ICIM-CIのモデル化事例をご紹介したいと思います。
.... 続きは、
からご覧ください。
───────────────────────────────────────────
■イベント情報
───────────────────────────────────────────
【1】【 PCB Systems Forum 2022 】
ユーザ事例とロードマップを交えながら、最新ソリューションを紹介。
9月8日(木)〜 今年はライブ&オンラインのハイブリッド開催 〜
ライブ会場: 東京コンファレンスセンター・品川
https://event.sw.siemens.com/pcb-systems-forum-2022-japan/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
LSI・パッケージ・ボード(LPB)相互設計規格である国際標準IEC 63055/
IEEE 2401-2019は下記URLからご購入できます。
https://standards.ieee.org/standard/2401-2019.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Jeita SDTC http://www.jeita-sdtc.com
LPB Forum http://www.lpb-forum.com
Facebook https://www.facebook.com/lpbforum/
Twitter https://twitter.com/lpb_forum
◆本メールマガジンは、LPBフォーラムに御参加いただいた皆さまに
各種イベントやセミナー情報を配信させていただくものです。
配信停止は下記URLからお手続きください。
配信停止用URL: http://jeita-sdtc.com/xmailinglist/news/
◆新たに配信をご希望される方は下記URLからお手続きください。
※このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。このままご返信
いただいてもお答えできませんのでご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C) 2017 JEITA 半導体&システム設計技術委員会
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━